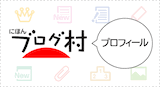朝8:50に本屋さん前へ。
ここは街で唯一のラオス語の本が売っている本屋さん。
Big Brother Mouse
https://www.bigbrothermouse.com/
寄付もできるし、本屋さんの中にある奥のちょっとしたスペースで、
子供達が英語を勉強している。
その勉強の先生にボランティアで飛び入り参加できる気軽さが、旅人たちにはちょうどいいのかもしれない。
前日のプーシーの丘の後、ふらっと寄って、本屋さんの説明や学校の説明などを英語で受けて、「私も何かボランティアしたいんだけど。。。」と伝えた。
(この時の自分は、完全に自信を無くしていた。
過去、カンボジアで孤児院に行った時に、子どもたちから元気をもらったことを思い出し、役に立ちたいというよりも、子どもたちから元気をもらいたいという、ボランティアをするにはなんとも不純な気持ちだったが、それでも役に立てることがあればと思い、頑張って伝えた。笑
支えてくれた友人たち、旅の中で勇気づけてくれた方々、本当にありがとうございました!!)
「じゃあ明日、学校に行こう!8時50分に来て!」
と約束をした。
お昼ご飯代と足代と寄付代等々でUS10$を渡し、早速、迎えの車で、いざ学校へ!
めっちゃ揺れるやーん!
そうなんですよ。知っていました。発展途上国ですもんね。
日本みたいに道が舗装されているわけないよねーーー!
牛さんいるーーーー!
頭打つーーー!
と揺られ揺られたどり着いたのが、下は3歳くらいかな?上は10歳くらいの子どもたちが通う学校。

自然がいっぱい。自分が通っていた幼稚園も裏山があって、いつも先生や友達と登って遊んでたな。最近の幼稚園は都会にあるから自然と離れ離れ。。。寂しい。
と、日本の教育環境に少し胸を痛め、先生たちと少しお話し。

3、4、5歳の子供達に英語を教える。
絵が描かれているカードを見せて、
「apple!」「APPO-」
と繰り返し声を出させる。
途中、不意に関西弁で「ちゃうちゃう!」って言ったら、
子供達も「Chau Chau!」って真似したから、
気をつけないとと焦った。笑
他の先生と30分ごとに交代して、気がつくとお昼だった。

先生たちと一緒に同じご飯を食べる。
同じ釜のめしがなんちゃら。。。
日本にはそんなことわざがあって。。。
「同じ釜の飯を食う」
意味:他人同士だが、生活を共にし、苦楽を分かち合った親しい間柄のたとえ。
日本は核家族が増え、一人で食べることが多い世の中で、誰かと同じ釜の飯を食う幸せさを忘れていたなと。
同じご飯を食べれて嬉しかった。
午後は少し坂を登ったところにある8歳前後のクラスで、再び英語の授業。
30分ほど英語でカードゲームをしたら、5分ほど体操して、次のクラスへ。。。
懐かしい。子供達も笑顔だった。
みんな、「Hello!Hello! I like flower! I like Mango!」
とぐいぐい自分の気持ちを伝えてくれる。
のびのびしてるなー
自由だなー
と心があったかくなった。
ボランティアをすると、こちら側が笑顔になるというのは、本当だと思う。
子どもたち、先生たちありがとう!
[ラオス事情]
といっても、子どもたち全員が学校に通えるわけではないらしい。
先生というのは公務員という立ち位置だけど、国からのお給料が滞っていたりもする。
なので、教育がちゃんとできない学校も少なからずあって、そんな学校なら行かずに家業を手伝いなさいという親もいる。
考えさせられる状況だった。